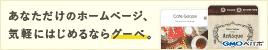ブログ
花は自分が咲く場所を選べるのだろうか?
花は自分が咲く場所を選べるのだろうか?
選べない、でも私たちは選べる。
人生を「自分の思い」で咲かせるための3つの視点
ふと、立ち止まって自問したことはありませんか。
「今の場所で、本当に自分らしく咲き誇れているだろうか?」と。
キャリアや日々の暮らしの中で、ボクたちは自分のいるべき場所や進むべき道に迷いを感じることがあります。
そんな時、道端に咲く一輪の花に目を向けてみてください。
誰に見られるでもなく、ただひたむきに空を目指すその姿は、私たちに人生における大切な何かを教えてくれます。
ちょっとポエムな書き方ですが、ボクの顔を想像せずによんでね。
そんな生き様り花を手がかりに、私たちが自分の人生を「自分の思い」で咲かせるための3つの視点を探求していきます。
--------------------------------------------------------------------------------
1. 「咲く場所」は選べなくても、「咲き方」は選べる
花はその場で咲くしかない。
たとえそれが日当たりの良い花壇であろうと、
人通りの少ない道端であろうと、
与えられた場所で根を張り生きる。
その姿に悲壮感はありますか?
そこには「道端でも花壇でも、そこで咲くなら咲き誇ってみたい」
静かな決意があるのか。
別に決意も何も、ここで咲くから咲いて魅せる。
その意志だけのような気もします。
「置かれた場所で咲きなさい」という言葉は、
時として諦めや現状維持を促す言葉として捉えられがちです。
その本質は。
それは、変えられない環境を嘆くのではなく、
その制約の中でいかに自分を最大限に輝かせるか、
力強い意志の表れなのです。
環境がどうであれ、自分自身の「咲き方」を選ぶことは、誰にもできるのです。
それが幸と出るのか不幸と出るのか。
それは今はわからないでしょう。
「その時」が来るまでわからないでしょう。
--------------------------------------------------------------------------------
2. 「選ばれること」が、真の自由とは限らない
道端に咲く花が、ある日誰かに「摘まれる」ことがある。
それは一見幸運な出来事に見えるよね。
キャリアにおける昇進や引き抜き、他者からの高い評価も、
この「摘まれる」という行為によく似ているのか。
認められ、選ばれることの魅力は抗いがたく、
差し出されたその手を取ることで、道が開けるように感じられます。
しかし、その先に待つのが真の自由とは限りません。
摘まれた花は、確かにその場から動くことができます。
けれど、その行き先は自分で決めることができるのか?。
摘まれたら動けるけれど、自分の行きたい場所とは限らない。
途中で捨てられるかも、
生けられるかも。
美しい花瓶に「生けられる」人生。
きれいに飾られ、多くの人から称賛される生き方も、それはそれで良いのかもしれません。
けれど、もし叶うのであれば、やはり「我が思いの中で咲きたい」と願うのが、
ボクの心の奥にある本質だと。
他者の選択に身を委ねる安堵感と引き換えに、ボクは自らの意志を手放していないか、深く問いかける必要があります。
--------------------------------------------------------------------------------
3. 私たち人間が持つ、たった一つの決定的な力
花とボクとの決定的な違いは何でしょう。
それは、自分たちの「意志」で動ける。コレかな。
ボクは咲く場所が気に入らなければ、自らの足で新たな場所を探すことができます。
この「意志」こそが、不毛に思える場所であっても自分だけの咲き方を定め、
差し伸べられた手が、真の目的地へと導くのか、それともただ美しい飾り物の花瓶へと誘うだけなのかを見極める力となるの気がします。
美しく飾ってもらえるならば、それはそれで嬉しい。
心の内に響く、静かに何度も話しかけるなにか。
周りの声や環境に流されるのではなく、
自分がどうありたいのか、
どこへ向かいたいのかを問い続ける。
ボクたちの「意志」は自分を育てようという呼びかけに応えることができるのです。
その先に、自分だけの道が拓けていきます。
ただ、その先というか道は開けているだけで、不毛なのかもしれない。
--------------------------------------------------------------------------------
うん。なんというか…。:未来へと思いを馳せる結び
花の生き様は、ボクに大切なことを教えてくれます。
咲く場所は選べずとも、咲き方は自らで決められること。
他者に選ばれる華やかさ。
それが必ずしも自分の望む自由と一致するわけではないこと。
そして何より、ボクには、自らの意志で人生を動かしていく決定的な力があるということです。
…けっこう優柔不断ですが…。
花は、ただその場で咲き誇ります。
ぼくは意志を持って自分の咲く道を選ぶことができます。
その選択肢があること自体が、僕たち人間が持つ最大の希望なのかも。
今日、ボクははどんな「意志」を育てるか?
そして明日、「きみは」どんな「思い」で咲きますか?
などと、ポエマーな記事でした。
ついでに。
今日9月の27日土曜日。蛹が羽化しようとしてました。
途中で力尽きてました。
あと少し。
くもり空でしたが、翔び立つチャンスがあったのでしょうが。。。
今目の前にチャンスがあります。
事実として動けるのですから、羽を動かすことができるのですから、羽を動かしてみましょう。
少なくとも君たちは飛べるはずです。
飛ぼう。
跳んで見よう。翔べるよ。
飛べ。
お金の黒帯その②~年収5万円アップはすごいよね。40万円は超凄い
毎月の出費を削れば「昇給」と同じ!
格安SIMと家計管理で遠征費をつくる
こどもが「カラテ」に打ち込む姿は、何よりも嬉しいものです。
その成長の瞬間を、できるだけたくさん見守りたいですよね。
しかし、活動の場が広がるにつれて、遠征や大会の交通費、宿泊費といった出費はかさむ一方。
「子どもの応援はしたいけど、正直、家計が…」
そう感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
給料を上げるのは簡単ではありません。
会社の評価を待ったり、新しいスキルを身につけたり、時間がかかるのが現実です。
でも、安心してください。給料を増やすことよりも、もっと早く、簡単に「お金」を増やす方法があります。
それは、支出を減らすこと。
例えば、毎月5,000円の支出を削減できれば、それは年間にすると6万円。この6万円は、地方で行われる大会に3回分参加できる交通費になるかもしれません。
いや、家族旅行に行きましょう(^^)
これは、給料を6万円アップさせるのと同じ効果 です。
会社の給料で増やすとナルト……。た、たいへんですよね。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
家計管理は「構え」と同じ
空手では、どんな技を繰り出すにしても、まず基本の「構え」が重要です。
構えがしっかりしていないと、どんなに強力な突きや蹴りも威力を発揮できません。
家計管理も同じです。
どんなに一生懸命働いても、**家計の「構え」(=固定費)**がブレていたら、
ガクガクブルブル・・・お金はなかなか貯まりません。
まずは、家計の「固定費」という隙をしっかり締めることから始めましょう。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
固定費削減の威力
固定費とは毎月決まって出ていくお金のこと。
例えば、スマートフォンの通信費、保険料、サブスクリプションサービスなどがこれにあたります。
一度見直すだけで、毎月のお金が浮きその効果は継続します。
-
格安SIMへの乗り換え 大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、毎月数千円安くなることは珍しくありません。お子さんのスマホ代も含めて見直せば、月10,000円削減も夢ではありません。
-
保険の見直し 「なんとなく」で入っている保険はありませんか?今のライフスタイルに合っていない保険は、無駄な出費につながることがあります。
専門家に相談して、本当に必要な保障だけにするのも一つの手です。
(保険屋さんに相談すると、新たな保険を勧められます。無料のファイナンシャルプランナーにソンダンすると保険を勧められます。コレ以上書くと怒られます。) -
サブスクリプションサービスの整理 動画配信サービスや音楽アプリなど、契約したものの、ほとんど使っていないサービスはありませんか?定期的に見直して、不要なものは解約しましょう。
携帯節約一万円。保険とサブスク見直し二万円2つ合わせて三万円。
さて、小学生の算数 3万円✖12ヶ月= 36万円。
もう一度書きます。
よく見てください。メガネかけてみてください。
36万円です。
ママ、化粧品ランクアップできますよ。
でもね…それよりもね。
化粧品も最低限度でいいよ。
できるだけ速く寝よう。
お肌にいいね。
コレで数千円
年に三万六千円節約としましょう。
36+3.6=39.6≒400.000 です。
40万円です。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
節約は「昇給」と同じ効果がある
「毎月5,000円削減」と聞くと小さく感じるかもしれません。
しかし、この効果を給料に換算すると驚くべき数字になります。
-
毎月5,000円削減 → 年間で6万円
-
手取りで6万円増やすには、税金や社会保険料を考慮すると、
会社から約8万円の昇給が必要
つまり、1時間の手続きで格安SIMに乗り換える。
それだけで、実質的に年8万円の昇給と同じ効果を得られるのです。
これはまさに、空手の基礎稽古と同じです。
いや、それどころの話ではない。
地味で目立たないかもしれません。
でもね、毎日の突きや蹴りの積み重ねが力の入れ場所の意識など、
やがて大きな力となるように。
コツコツと固定費を削ることで、将来の家計を強くすることができます。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
まずは「スマホ代」から
いきなり家計簿をつけるのは大変かもしれません。
まずは、一番効果が出やすいスマホ料金から見直してみませんか?
乗り換え手続きもオンラインで簡単に済ませられます。
たった1時間の手続きで、来月からはずっと5,000円節約できるとしたら。
試してみる価値はあると思いませんか?
削ったお金は・・・パパに内緒でお友達とランチへ(^^)こっそりと。
いや、違う。子どもの「挑戦」に使いましょう。
お金の面からも支えることができます。
空手の稽古と同じように、家計管理もコツコツと。
その積み重ねが、お子さんの未来を力強く支えます。
これも、たまにトップ記事に持ってきます。
デビュー戦に向けて
お金の黒帯その①「空手を続けるには“お金の黒帯”も必要!教育費と習い事費を両立する家計術」
人生の⑨割のことは「お金」が大事。
…いいすぎか。。。
「空手や格闘技って、他のスポーツに比べてあまりお金かかりませんよね。でも、道具代、遠征費…そして将来は大学費用も待っている」
現実の課題提示は
-
習い事費+教育費の両立の難しさ
-
親御さんが一番悩むポイント(お金が理由で辞めさせたくない)
長い指導生活で、家庭の話も聞かせていただき。
相談され。自分にお金がないために、力になれなかったことも多々あり。 -
解決の方向性
-
短期:家計管理・クレカ活用・固定費削減
7年以内 -
中期:貯金と学資準備
5年から10年 -
長期:新NISAで積立(オルカンなど優良ファンド)
10年以上
(証券会社を間違えないように。信託報酬で利益持っていかれます。)
-
-
空手に絡めた比喩としてはこんな感じかな。伝わるかな。
-
「空手は1日で強くならない。お金も一発逆転はない。コツコツ積み重ねて黒帯になる」
-
「毎月の積立=毎日の稽古。継続が最強」
-
-
まとめ
「子どもの成長を支えるのは先生や仲間だけじゃない。
家庭の“お金の準備”も同じくらい大事。
空手とお金、両方の積み重ねで未来は広がるからね。」
ボクが気にすることではないかもしれないけど。
だから、「お金の学び」として、お金持ちでないボクが(^^)
記事を書いてみたいと思います。テヘっ(*ノω・*)テヘ
★☆★ではでは、始まり始まりぃ~。★☆★
* ソレナリの収入と家計・支出の管理できている方には必要ない内容です。
稽古と同じくらい大切!いやっ。それ以上「お金の知識」
空手やキックボクシングを頑張っている子ども。
そしてその成長を温かく見守るパパにママ
いつもありがとうございます。
指導者として、日々皆さんの気持ちに応えるべきと、優しさに厳しさと、どこで境界線を引くか考え指導しています。
技を習得し、心身を鍛え、仲間と切磋琢磨する。
その一瞬一瞬が、学びに成ればいいなと。
しかし、指導者という立場でお話しをさせていただく中で、子育てや習い事にかかるお金について、悩みを打ち明けてくださる親御さんも。
「空手は他のスポーツに比べてお金がかからないと思っています。」
特に鴻凛會・KRKgymは道具代や遠征費、審査料など、他の団体に比べてかからないと思います。
安いわけではないですが(^^)。、鴻凛會の場合はあまりかからないと思います。
(^^)たぶん。
「できれば長く続けさせてあげたいけど、兄弟の他の習い事に塾に…。この先、大学費用も考えると不安で…。」
お金が理由で・・・。
そんな少し寂しい選択をさせたくない。と、誰もが思っています。
僕自身学費のない家庭だったので、目指したい場所を探すのは最初からしないほうがいい。
そういった悩みに直面し、力なくダラダラと生きていた自分もあります。
・・・今もあまり変わらないかな☹️
だからこそ今、皆さんに伝えたいことがあります。
子どもの成長を支えるのは、先生や仲間だけではありません。
家庭における「お金の準備」も、同じくらい大切です。
空手とお金に共通する「コツコツ」の力 。
空手は一日では強くなりません。
毎日の地道な稽古の積み重ねが、やがて強固な実力となって表れます。
失敗とか、辛さとか。
その経験を、どう変えるか。
捉え方を変える。
見方をかえる。
言葉を変える
行動を変える。
起こったことを受け入れ、
変えられないことを納得し、
変えるべきところを変える工夫。
これは、お金の準備もまったく同じです。
お金に「一発逆転」はありません。
宝くじで一攫千金を夢見るのではなく、毎月、着実に積み立てていく。
雷に打たれる確率
雷様に会う確率
「高木ブー」さんに合う確率。
宝くじに当たるほうが確率低いらしい。
しらんけど…(^^)
この「毎月の積み立て」は、日々の稽古と同じです。
今日できなかった突きや蹴りも、毎日練習すれば必ず上達する。
それと同じように、毎月コツコツと積み立てる。
将来、子どもの選択肢を広げる大きなお金の力となります。
お金の準備は、空手の帯の色と同じ 。
具体的なお金の準備は、空手の帯の色を上げていく過程に似ています。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
短期計画部門 (7年以内):白帯という準備期間・現金で持っておきましょう
まずは家計の現状を把握しましょう。
どこにお金が使われているのかを知ることで、無駄をなくすことができます。
電気を小まめに消すよりも、スマホを格安SIMにしましょう
5000円は安くなる。すると、✖12で6万円
まるが、0000 4つもつくきます。そう6のあとに0000
即ちですね。¥60.000。
家族三人で ¥180.000
年間ですよ。
さぁ!家族で一泊二日美味しいもの食べる旅行に行こう。
あと、保険も見直そうね。
日本人ならすでに、世界最強の保険に入ってるよね。
毎月の固定費を見直したり、クレジットカードを賢く活用したり。
家計管理の基本を身につける期間です。
必要ないサブスクも解約を。
例えば・・・たまに映画館に行ったほうが楽しいよ。
保険は「保険という名前の投資をしています。」
学資保険・・・いくら増えますか・・・。
昭和の保険のない時代。将来が視えない時代。高度成長期の時代。
今は「令和」
中期計画部門( 5~10年):色帯の応用期間・現金と投資(自己投資と優良ファンド)
ある程度の家計管理ができるようになったら、次は貯金や学資準備を始めましょう。
自動で積立ができる仕組みを作っておけば、無理なくお金を貯めることができます。
(積立保険とかのことではないよ。あまり書くと色んな人に注意されたり・怒られたり・うらまれたり。。。。)
現金はインフレ負けします。100円の缶コーヒーも120円な。
お米はすでに2倍
長期(10年以上):黒帯の継続期間
これはまさに、空手の稽古と同じく「継続が最強」の領域です。
今話題になっているNISAなどを活用して、長期的に資産を育てていくことを考えましょう。
投資と聞くと難しく感じるかもしれませんが、毎月少額から始められる「積立投資」なら、初心者でも無理なく始められます。
親子で一緒に「お金の道場」に通おう 。
あ、言い過ぎました。
空手は、心技体を鍛えるだけでなく、目標に向かって努力すること。
そして何より「工夫」を学ぶ場です。
金融の知識も同じです。
親御さんが学び、実践する姿を見せることは、お子さんにとって最高の金融教育になります。
「なぜお金を貯めるのか」「どうやってお金を増やすのか」 そんな話を親子で一緒にすることで、お子さんは将来にわたって生きていくための「お金の力」を身につけることができます。
子どもの成長をサポートする上で、先生や道場の仲間、そしてご家庭の「お金の準備」は、すべてが繋がっています。・・・かな。
空手と金融、両方の「積み重ね」が、お子さんの未来を豊かに広げてくれるはずです。
私たち指導者も、お子さんの成長を応援しています。
このブログが、少しでも皆さんの不安を解消し、前向きに未来を考えるきっかけになれば幸いです。
一緒に、子どもの未来を、そして自分の夢を応援していきましょう。
すごく立派なことを、立派ではないボクが書きました。
でも、失敗とか、本を読むとかは、いっぱいしました。
だから、信用はできないでしょうけど、ブログは参考にしてください。
立派な人が書いた内容を、ボクなりですが、文章記事にしています。
この記事は極たまに、トップへと投稿します。
大事だと思うから。
心構えシリーズ⑨~技術だけでは勝てない。勝敗を決める「心の準備」とは?
【試合に向けた心構え】技術だけでは勝てない。勝敗を決める「心の準備」とは?
どれだけ厳しい稽古を積んでも、どれだけ技が上達しても、試合本番で実力を出し切れない選手は少なくない。
その原因の多くは―― 「心の準備不足」 かも。
試合の勝敗は、当日の技術や体調だけでなく、前日から会場に向かうまでの 「心の持ちよう」 に大きく左右されますよね。
今回は、試合を控える選手や、これから挑戦したい人に向けて、「試合に向かう心構え」をお伝えします。
1. 試合の「恐怖」を「期待」に変える
試合前に緊張や不安を感じるのは当たり前です。
「相手はどんな選手だろう…」
「もし負けたらどうしよう…」
大切なのは、この 不安を無理に消そうとしないこと。
その「恐怖」を「期待」に変えてみましょう。
と、いわれても。。。
わかるよぉ~。
-
「今まで練習してきたことが、どこまで通用するか試せる!」
-
「新しい自分に出会えるチャンスだ!」
-
「応援してくれる人に成長した姿を見せられる!」
試合は怖いものではなく、自分を成長させてくれる最高の舞台です。
上に書いたように思えるといいよね。
・・・難しいかな?。
うん。気持ちはわかる(^^)
2. 「成功のイメージ」を鮮明に描く
試合前には、できるだけ具体的に「成功している自分の姿」をイメージしましょう。
-
自分が最高の動きをしている姿
-
攻めて攻めて、思い切り戦っている姿
-
試合後に清々しい気持ちで相手と握手している姿
イメージは完璧でなくても構いません。
むしろ「多少失敗しても、前に出て戦い続けている自分」を描くほうが、当日の動きにつながりやすいのかも。
成功している自分の姿を想像するのも…チョット…。ならば妄想しよう(^^)
想像だろうと妄想だろうと、稽古してきたのなら、自分は動くし、攻撃し続けるし、ヤラれるなら見事に負けてみせる。
そんな気持ちで行こうね。
3. 「勝ち負け」にこだわりすぎない勇気
もちろん、勝利を目指すのは大切。
しかし「勝たなければならない」という強い思い込みは、心と体を固くしてしまいます。
試合の本当の目的は――
「練習の成果を出し切ること」。
-
技を出し切る
-
動き続ける
-
反則しない
-
後悔を残さない
多すぎる?ならば!
俺は動き続ける!!
そう言って、それをヤロウ。
これだけを意識すればOKです。
勝敗はその後についてきます。
見事な負けっぷりを魅せような。
まとめ|緊張してもいい、動き続けろ
試合は、普段の稽古の成果を見せる場であり、自分自身の「心」と向き合う舞台です。
-
緊張や不安は「期待」に変える
-
成功のイメージを描く
-
勝敗よりも「全力を出し切ること」を大切にする
やっぱり・・・無理・・・。その思い。
構わない。
動こう、ヤロウ。
とにかく大事なのは、 緊張したままでも動き続けること。
攻撃して、動き回って、自分を表現し尽くしましょう。
そうすれば、きっと後悔のない最高の戦いができます。
・・ま・・ああすればよかったとか・・・後悔はあるかな。。。
始まったら動くしかない。動いて、そしてヤルの。
ガンガンヤル。
頑張って!ボクは健闘を心から応援しています。
かっこよくやろうとして相手をみすぎたり、しっかりやろうとしない。
実力のあるベテランじゃないんだから。
そんな事やってると、「後手」になります。
「先手」「先の先」「後の先」とにかく間髪入れない。
自分からね。
自分から攻撃してもよし。
自分から左右に動いて相手に攻撃させてもよし。
動け! ヤレ! ヤル!