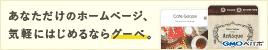ブログ
鴻凛香語
組織の定義づけ 共通のものの見方。理解。方向付け。努力の実現するには
『われわれの事業は何か、何であるべきか』
つまり、鴻凛会とはどういう組織で、何をするべきか
鴻凛会とは 威風堂々と凛 羽ばたいて鴻
自分の身体の使い方を得とく活用し、
心身の聡明さと爽快さを保ち暮らす。
オシャレと笑いと香り。人は寝たきりにならずに生きていける。
20代の身体は無理でも元気な90代にはなれる。
歩けるし投げれるし、踊れるし笑える。自由自在でいれる。
自分以外の人に自分を表現し楽しみ感じてもらう
微笑み言葉と信頼言葉。 自由自在をサポートする。
身体が硬くても『しなやかさ』があるように。
180°脚が開かなくても100°しか開かなくても、
その100°で自由自在に使いこなせるように。
心身の機能を発達維持させ、60代でも30代のつもりで、
自分自身が勘違いするほどアドバイスサポートしたい。
90代でも自由自在
鴻凛カラテとは 自己最良の鍛錬を楽しみ、自身の最強を造る。
地上最良・自己最強である。
顧客 そして顧客とは・・うちの場合(僕の場合?)生徒・会員
にあたる。
いわゆる僕の弟子。
鴻凛会の顧客は・・・社会?
僕の顧客の要求・満足は
生徒自身。 要求は強くなること・カッコよさ・美しさ・楽しさ・
称賛受けて誉められること・
男の子などは人より有利になること・
女の子はみんなでカッコよくあること
満足は 信頼をもって人格ある個人として接する
親御さん。 子供の自信・素直さ・礼儀・行動力・優しさ・
子供を通じての親の称賛。感動
満足は 自らの言葉と行動の素晴らしさを魅せてもらうこと
先生自身に対しては 凛とした雰囲気。
信頼にたる振る舞いユーモア・優しさ。
鴻凛会の顧客の要求・満足は
要求は 感動・凛々しさ・礼儀正しさ・健康
満足は 武道家然とした態度の挨拶・振る舞いを感じたとき
今日をだらだらと無為に過ごす。明日も同じこと。
そして次の日はもっとぐずぐずする。
ゲーテ(詩人)
吉田松陰は、「すべては瞳にあらわれる」と言いまし
器 2・螺旋
自分の“器”を、自分で変えよう。
道場は。
君が (ボクかな(^^)) 育てるべきは、技術だけじゃない。
「人物としての器(うつわ)」そのもの。
器は、勝手には大きくならない。
必要な知識を仕入れたら、
それを 実行・実践しよう。
行動して、ふり返って、改善して、再挑戦!
これを何度も何度もやる。
回して、まわして、PDCAサイクル。
同じところをぐるぐる回ってるようで、
前回にも書いた。
螺旋階段”を登るように、上昇している。
器が大きくなるとは、こういうこと。
・前は受け止められなかったことを、受け止められるようになる。
・反発してたことを、受け入れたり、活かせるようになる。
・今まで無理だったことに、再挑戦する勇気が湧く。
そして、あふれた分は?
器がいっぱいになってあふれてきたら、
そうです。その時こそ考える。
「これは、どうやって今の器に収めよう?」
「もし無理なら、どうすればもっと大きくなれる?」
そうやって、自分自身に・問い・を投げかけてみよう。
その問いが、次の成長のカギになる。
君の器を変えられるのは、君自身だけだ。
実行・反省・改善・再挑戦――この螺旋を、登っていこう。
と、自分に言い聞かせてみるボクでした。
きつい練習が楽しい!それは自ら楽しげに積み重ねる
一人で踊ってます。
一人じゃないとおもっていた?
曲は変えてます。ナルトじゃないです。
17時から21時近くまで稽古。
途中休憩と、ソーセージ系のもぐもぐタイムを挟んでますが。
カナタとカナタ。
よく足上がっています。
二人のケリはかっこよい。
もちろんムッキーも。
ムツキの動きは矯正したい部分が多いのですが、
日々見ていて、動画?かな。
それとも自分で考えている。
過去に指摘した技のつなぎ方とか意識している?。
よくわからないけど、本当によく進化してます。
カタツムリのような進化スピード。
しかし、気づけばそれなりの距離進むし、指数関数的に進む瞬間が現れるでしょうね。
実際、今の体重でキックボクシングすれば、かなり自分のファイトスタイル表現できるでしょうね。
合同稽古終われば、色々体で覚えるために、補強とかトレーニングの仕方とか、
経験してもらってます。
「りょうた」もジワジワ進んでます。
彼の場合は気性をモット激しくデキるといいのですが、おとなしすぎかな。
でも、ケリは進化するし距離も得意な間合い分ってきてるし。
せめてパワーアップしてもらいたいね。
頑張ろうな。やる分には、全部教えるから。
奥に映る「たいし」もね。
性格も良いし、センスは抜群・・・ただ、「キャーッ」といって逃げるのは(^^)
動きはカッコいい。
俺が一番。ぐらいの気性で、稽古して、試合に挑もう。。
ボクはスパーでも動けない。
ケントや高校生「りょうた」相手なら、カッコだけでもなんとかなるけど・・・
めぐ先生に・・・笑われてます。(^^)現実は受け止めよう。
陰から力使うね。。
周りの生徒に貢献する。
ちなみに高校生「りょうた」センスは抜群。
ウダウダするのがナァ~。。
ケントは社会人。
定期的に稽古が出来ないのは致し方ない。
だから、いろいろ、生涯役立つ技術教えていってます。
さぁ、8月も近い。お盆休み過ぎたらまた試合向けの稽古・練習。
生徒個人・個人のメニューつくる。
頑張るぜぇ~![]()
質問する技術④。知識をひけらかすのではなく、相手の成長のためにどう「渡す」か
「質問が出ない」そのとき——これでいいのだろうか?
知識をひけらかすのではなく、相手の成長のためにどう「渡す」か。
これは、僕が今もずっと試行錯誤している部分です。
指導していて、ふと立ち止まる瞬間があります。
「質問が出てこない」のです。
ここまで読んでくださった方の中には、
「小嶋先生の指導なら、みんな納得してて質問なんて出ないんじゃないですか?」
モット褒めてもいいよ。
そんなふうに言ってくださる方もいるかもしれません。
実際にやってみて、体で実感してもらう稽古を大切にしています。
そこには、理論や理屈もありますし、経験からくる現実も深く込められている自負もあります。
生徒たちが「先生の言う通りにすれば間違いない」と信頼してくれていることも感じています。
それは、指導者として本当に光栄なことです。
でも、それでも僕の心の中にはいつも、
「コレで・・いいのかなぁ~?」という問いが横たわっているんです。
★なぜ、質問が出ないのか?
僕は基本的に、高校生以上には「一つ教えたら、黙って見ている」スタイルでいます。
質問が出てきたら、その先を教えよう。そう思っているのですが……。
我慢できずにくちだしするけどね。
サンドバッグを打つ手は止まらない。
それぞれ真剣に稽古に向かっている。
それはとても誇りに思えます。
でも、質問がない。
不思議でならないんです。
僕はいつも稽古中に、疑問が次々に浮かんできた人間でした。
彼らは——
-
僕に聞いても仕方ないと思っているのか?
-
実はしっかり理解して、黙って吸収しているのか?
-
僕の指導が「説明の理解が、しにくい」から、逆に言葉にできないのか?
たまに、万人受けする言い方をすべきか……と考えることもあります。
それっぽく、素晴らしい系の言葉並べたくる。がいいのかな。
でも、世間で「もっともらしく」語られていることが、
すべての人にとって本当に役に立つかというと、そうでもない。
すごい人の話が、普通の人に役立つとは限らない。
でも、有名な選手等が言うと鵜呑みにしている子もいる。
「きみはタイプ違うと思うが・・・。」
有名選手は、さすがトップなだけ有る。才能があるのです。
きみは普通。
きみに向いているスタイルから作り込んで、トップに喰らいつこうよ。
それともボクがきみの才能に追いついていないのか・・・、。
質問が出ない理由——僕が考える3つのパターン
-
完全に理解し、納得している。
これは、理想的な状態です。 -
理解しているけれど、「問いを立てる力」がまだ育っていない。
もっと深掘りできる問いに、気づけていないだけかもしれない。 -
実は理解しきれていない。でも、「こんなこと聞いていいのかな」と遠慮している。
理解できない自分を、どこかで「申し訳ない」と感じているのかもしれない。
2番目と3番目の可能性を考えると、
僕の中でまた、「これで本当にいいのだろうか?」という問いが頭をもたげてくるんです。
質問されて、すぐに言葉に出来ないけれど、頭の中のイメージは出来てます。言葉として表現するのが難しいのです。そして今、やって見せることが出来ない現実があります。
許してくれ。
★僕が目指している指導
僕は、ただ技を教えたいわけではありません。
生徒たちが、自分で課題を見つけ、自分で答えを探し、自分で成長していけるようになってほしい。
だからこそ、僕の指導は「答えを教える場」であると同時に、
「問いを見つける手助けをする場」でなければならないと思っています。
【難しいですね。】
生徒が「これだ!」と納得できるほど、質の高い指導を追い求めながら、
同時に彼らが「なぜ?」「もし○○だったら?」と自ら問いを立てるような場もつくっていきたい。
「質問が出ない」ことに満足せず、
その奥にある可能性を、僕はもっと引き出したいんです。
★僕には先生がいませんでした
かっこつけて言うなら、**「我以外、皆我師」**です。
僕が格闘技を始めたころ、練習する場所も、人も、圧倒的に少なかった。
キックボクシングのジムなんて、今のようにありませんでした。
聞きたいことは山ほどあるのに、聞く相手がいない。
練習相手もいない。
たまに弟がミットを持ってくれるだけ。
だから僕は、ひたすら「試す」しかなかった。
考えて、仮説を立てて、試合の3分で確かめる。
あーでもない、こーでもない。
無駄が多すぎるかもしれない。
でも、やってみないとわからない。
そんな試行錯誤の連続でした。
誰かに聞きたくても、
ようやく聞けたときには、相手の答えがマチマチ。
時には、偉そうで上から目線で返されてしまったこともあります。
聞きたいのは、そんなことではない・・・。
……いや、僕が素直じゃなかっただけかもしれません(笑)。
★今、僕がやるべきこと
だからこそ今、僕が目指すのは、
「答えを与える」よりも、「問いを引き出す」指導。
質問が出ないときこそ、自分の指導を振り返る。
生徒が“自分から聞きたくなる”空気を、もっと意図的につくる。
それが、僕がこれからも挑み続けるテーマです。
ヤル、マカシとけ。
今日の練習で、誰かがぽつりと質問してくれるかもしれない。
その一言が、全体の成長につながるかもしれない。
その種をまくのが、僕の仕事。
問いの芽を育てる場所をつくるのが、指導者だと思っています。
と、思っていますが。
むずかしい・・・。
質問まつより、ドンドン、指導したほうが早い・・・。
これがイケないのか。
まつのも技術が必要ですね。
質問する技術
🔥質問できる子が伸びる理由
~勇気・技術・実力・が試される瞬間~
★なんで質問できる子って、伸びるの?
その理由は、説明されなくても大人ならばなんとなく解る気もする。
質問するけど伸びない子もいる。
大人でもそうですよね。
たぶん・・・行動に差があるのでは?
さて、まず、質問とは、たぶん・・「わからない」を「なるほど・・な気がする。」に変える行動。
-
質問できる=自分と向き合ってる
-
質問できる=その先に進もうとしてる
-
質問できる=相手とつながろうとしてる
質問とは、『前に進もうとする姿勢』そのもの。
進まない人は、ただの疑問と好奇心で「聞く」行動をしただけ。
🎯でもさ、質問って勇気いるよね?
うん、そう。
みんなそう思ってる。
-
「こんなこと聞いていいのかな…」うん、僕もよく思うよ。
-
「バカにされたら嫌だな」うん、これも思うよ。
-
「先生、イライラしてるし…」す・・すまん・・。
…そうやって、質問を飲み込む人はたくさんいる。
でもね、それでも質問するってことは、
「今の自分を超える」って決めたってことな。
🎧聴くには“技術”がいる
たとえば、誰かが質問してるとき。
それを聞き流してたら、成長チャンスを逃してる。
-
話のどこに“ヒント”がある?
-
何を答えて、どう返された?
-
自分ならどう質問する?
「他の人が質問しているのを聴ける子」は、
“他人の学び”を“自分の成長”に変えられる子だ。
と・・・思うのですが。
人の質問を聴いていて、「あっ」と思うことが有る。
人の質問を聴いていて、「そんな疑問があったんだ」と思う。
人の質問を聴いていて、「アイデア」浮かぶことも有る。
他人のしている質問も、聞き耳立ててみよう。
その人の性格も読めるかもよ。
🗣質問されて、応えるための説明には“実力”がいる
「どうやったら質問に答えられるか」
って、めちゃくちゃ考えるよ。
物事の説明って難しい。・・まじ難しい。
でもそれって、
「自分がどこまで理解してるか」が試されるってこと。
説明できる人は、理解が深い人。
つまり──
答える側にも“伸びしろ”があるってこと。
と・・言い聞かせて日々頑張っております。
💡だから道場ではこう言う
我が身にも、みんなにも。
「わからんかったら、聞け。」
「聞かれたら、応えろ。」
「応えられんかったら、次までに考えとけ。」
質問とは、
道場に流れる“学びのエネルギー”だ。
止めるな。流せ。まわせ。
・・・ながされるな・・・。
✅今回のまとめ
-
質問は“わからない”を“なるほど”に変える力
-
聴くのは技術、答えるのは実力
-
恥ずかしくても、質問する勇気を持とう
-
応える側も、責任を持って“学び返す”
-
質問が飛び交う道場は、進歩がある。
🤔きみへの問いかけ
-
今日、自分から質問した場面はあった?
-
誰かの質問を「自分ごと」として聴いた?
-
「応えたけど説明が曖昧だった」こと、ある?
質問って、その瞬間に世界が変わる一歩な。
僕も正しく解りやすく説明しようと、頑張ると・・・
・・・逆にわかりにくくしてしまうことが有る。
✅聞く能力上げるための一言
能力上げる・・・「一言」って有るのかな?
でも、質問する「環境」作ってあげないとね。
難しそう。
質問した気になる環境はダメだろうし。
緊張とともに質問してくるように、少し聞きづらい状態にはしている。
それが正しいのか、どうなのか、
・・・どうなのだろう。
質問できる子は、伸びる。
でもね、伸ばすのは「周りの環境」でもある。
「聞ける空気」「応える覚悟」「出た答えをやる行動」
それがあるチームは、強くなる。
君が質問すれば、誰かが応える。
君が応えれば、誰かがまた学ぶ。
それが、“学びが回る道場”。
君がまわしていけ。
文章でかくこと、道場で説明する言葉。
この2つでより良く、幅広く、深く、高々と、理解できるのではないかと、書きまくってます。
「読んだだけだとわからん」らしい。
説明受けて読むと判るらしい。
より良く、腑に落ちる。と嬉しい。
ただ、小学生には!?・・むずかしいかな。
なので誰かに、「なにか」を書いてもらう。つもりです。
感じることとか、アイデアとかにツナガルと嬉しい。
周りに語りかけているのか、自分に語りかけているのか。
そんな記事ですが。
誰にでもいいから質問してみよう。
同じ質問を2人・3人・としてみよう。
同じことを言っていても、違う言葉に聞こえるから。
🛍️書籍提案
📕『質問力』
(読んでないけど)広告
|
質問に関する本は何種類か有る様子。 齋藤孝さんなど、有名な方の本もあるようですけど、どれがいいかな。 できれば小学生にも分かる本。理解しやすい本。 本屋さんで探してみます。
|
📙『説明の技術』漫画系ならどうだろう。
広告。
|
|
これも読んでません。でも、わかりやすいのでは・・・。
縁尋機妙・多逢勝因