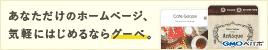ブログ
春よ来い。大人も日々進化中。
忙しい仕事の後に、約一時間ほどの稽古。
準備運動省くと30分から40分程度。
その時間でもコツコツ続け、アバラにもヒビが入り( *´艸`)。
それでもコツコツ頑張る男。
構えの姿も美しくなりました。
テクニシャン、ポイ構え。立ち姿が良いとかっこいい。
蹴りの伸びも素晴らしいものです。
なんだか春には別の男になってそうな気配。
構えた時の印象は一段と大きく見えるようになりってるから、
上達している証拠。
夏には盛ろうぜ。

で、キックの選手

こちらも仕事は三交代の選手。
( ^ω^)・・・リズム造るの難しいよね。
それでも稽古に来て、息あげから、テクニカルな稽古まで、
少しずつくみ上げてます。
言い方よくないけど、思い上がりの技術もある。
でも、それも大事。
どこが良くてどこが修正点か。
それがわかれば、思い上がりも抜群の成長材料。
今度の試合はKOでしめよう
向上心。やる気 負けん気 元気
「すごい」
何がすごい。
最近の静かな「ヤル気」
入門したての頃の『どうせ…」のセリフはどこへやら。
素晴らしいね。
「負けん気」までは派手に魅せませんが、その「意志」はあるのがわかる。
あとはしっかりと、周りのみんなが見てわかる『元気」が見えるといいね。
そこを見せると「魅力」という「力」つくよ。
頑張れ。
水曜日は空手の日です(^^)
毎週水曜日は空手の練習日なので
キックボクシングのクラスは使えません(^-^)
水色帯の子たちも上達してきてます!
身体を上手く使える様になってきたのかな?
昇級目指してる想真も今日は気合い入ってました
やっぱり気持ちひとつですね(≧∀≦)
学年も上がるから体力もついてきた気がします
日曜日、優勝を果たした恭太郎ですが
まだまだ覚えないといけないことが沢山!
彼の憧れの先輩「かなた」に弟子入り確定
頑張ってね(笑)
かなた&かなた❤︎
2人とも優しくてカッコいいです!
水曜日は初心者クラス
そのあと少年部という2部構成となってます
まだまだ空手の練習生募集中です!
見学は自由となってますが
その前に電話いただけるとスムーズです(^ ^)
キックボクシングの選手も募集してますので
お問い合わせ下さいね!
優勝おめでとう!
成長を感じます
鴻凛會です
月曜日と水曜日、そして金曜日の5:30〜6:30まで
超初心者コースを設けてます😊
めぐ先生のクラスとなります
そんな1時間コースですが皆んなの成長を感じてます
とにかく声を出す!
少しずつですが礼儀や挨拶も出来る様に👏
「ママが良い〜(;o;)💦」と泣いてた子たちも
イキイキと良い顔になってきました!
そりゃあ、ママがいて欲しいよね😊
何でも話し合える、考えて行動に移せる
そんな仲間になっていって欲しいですね!
違う学校、違う学年の子たちが仲良くなっていく
家庭、学校とまた違うコミュニティの場所として
道場があるのもまた良い事…
そう思ってもらえる場所になれる様に頑張ります
押忍!