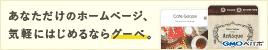ブログ
やる気の差ではありません――同じ指導なのに反応が違う理由 |パパ&ママへ。
※この記事は、道場で子どもたちと向き合う中で感じたことを、 親御さん向けに噛み砕いて書いたものです。 専門的な心理学の話ではありません。 一人の指導者・大人の視点として読んでください。
同じことを教えているのに、反応が違うのはなぜ?
道場でよくある光景です。
同じ説明をして、 同じ練習をして、 同じ声かけをしているのに――
・素直に取り組む子 ・ふざけたように見える子 ・黙り込む子 ・そっけない返事をする子
反応は、まったく違います。
これ、 「やる気の差」でも 「性格の良し悪し」でもありません。
子どもは、それぞれ“守り方”が違う
子どもはみんな、 自分なりのやり方で
心を守っています。
ある子は、 目立つことで自分を守ります。
・元気に振る舞う ・おどける ・ふざけて見せる
でも内心では、 「出来ないと思われたくない」 「恥ずかしい」
そんな気持ちを抱えていることも多い。
できないと思われたくない子もいる
一方で、
・考えてから動く ・慎重 ・失敗を嫌う
そんな子もいます。
このタイプの子は、 「分かりません」 「出来ません」
と言うこと自体が、とても苦手。
だから、 ・曖昧な返事 ・調子が悪そうな態度 ・素っ気ない反応
になってしまうこともあります。
どちらも「悪い態度」ではありません
大事なことなので、はっきり書きます。
どちらも、悪い子ではありません。
ふざけているように見える子も、 そっけない子も、
不安や緊張を 自分なりに処理しているだけ。
思春期は、さらにややこしくなる
成長すると、 「自分で決めたい」という気持ちが強くなります。
その結果、
・親の言葉に反発する ・会話が減る ・態度がきつくなる
そんなことも起きます。
これは、 親御さんの育て方が悪いわけではありません。
成長の過程で、ほぼ全員が通る道です。
親ができる一番大事なこと
親御さんにお願いしたいのは、
「比べないこと」
兄弟と比べない。 友達と比べない。 昔の自分と比べない。
その代わりに、
・昨日より少し前に出た ・前より続けられた ・逃げずに挑戦した
そんな過程を見てあげてください。
褒めるより、「認める」
「すごいね!」 「上手だね!」
もちろん悪くありません。
でも、それ以上に大事なのは、
「頑張ってたね」 「工夫してたね」 「逃げなかったね」
結果ではなく、 そこまでの道のりを 言葉にしてあげること。
指導者は、子どもを“育てる人”ではない
少し意外かもしれませんが、
指導者は、 子どもを親の代わりに育てる存在ではありません。
子どもが挑戦できる 「場」をつくる人。
親御さんと指導者で、 役割は違っていていい。
最後に
子どもは、 大人が思っている以上に、 ちゃんと見ています。
見られていることも、 信じられているかどうかも。
焦らず、 比べず、
「この子なりのペース」を 一緒に信じていきましょう。
それだけで、 子どもは少しずつ前に進みます。
凡事徹底②×こども
いつものこと。
やらなきゃいけないだけのこと。
人生の技術。
と言っていいのかな?。
何をするにしても大事な部分。
本人も慣れてしまえば気づかない。
日常の成功体験。
修行僧のように規律正しくする必要はないと思います。
挑戦が普通になる指導。
失敗も成功も日常。「凡事のこと。」
気をくれするでもなく。
焦るでもなく。ただ、挑戦と工夫とが日常になります。
失敗したらどうしよう。
そんな悩み…僕は嫌でした。
いまだにあるけど('ω')。
みんなに失敗は楽しいこと。
次への工夫で自分が成長することと知ってほしいかな。
…自分へも言い聞かせたい(^_-)-☆。
姿勢①
その時にあった立ち姿を
【姿勢の美しさ】だいじよね。
――立ち姿で勝負は始まり、終わっても続く――
試合会場で、まだ試合が始まっていないのに「強そう」と感じる選手がいる。
技を出す前から、もう“勝負”は始まっているね。
立ち方。
目線。
身体の力の入り具合。
わずかな重心の位置。
そのすべてに「日々の稽古」と「心の在り方」がにじみ出ます。
難しいよね。
いまだに僕もできてないと思う。
■ 姿が語るもの
空手に限らず、立ち姿はその人の“生き方”を映します。
焦りがある者は揺れ、慢心がある者は傾く。
心が整った者は、ただ静かに立つだけで空気を変えます。
試合で、どちらも互角のとき――
その一瞬の「立ち姿」で、勝敗が決まることもあります。
それは、技ではなく「品」。
形ではなく「魂」。
そう姿勢です。
■ 試合のあとにも、勝負は続く
試合が終わり、判定を待つ時間。
このときの姿こそ最も見られている。
勝っても驕らず、負けても崩れず。
まっすぐ立ち自信に満ちた姿。相手を敬う姿。
それが“勝者の立ち姿”かな。
勝敗のあとにも、勝負は続いている。
勝っても負けても、試合会場を降りる姿。
控室の姿。
そこにいる姿こそが、本当の「自分」としての価値を映す。
…難しいよね。僕もできてない('ω')
■ 立ち姿を磨く稽古
立ち方を整えるとは気持ちを整えること。
そして「音色」を整えること。
耳に聞こえないけど聞こえてきそうな「音」
目に見える「音」
目に見えないけど感じる「色」
耳に聞こえるその人の「色」
姿勢の美しさは、呼吸・礼・目線・足裏の感覚、すべての積み重ね。
毎日の立ち方、礼の仕方が“試合の顔つき”をつくります。
立ち姿は、「静の型」。
どんな型よりも、その人の人生が出る。
かもね。(^_-)-☆
🥋まとめ
-
試合は、立つ瞬間から始まる。
-
勝敗は、終わったあとにも続いている。
-
姿勢が整えば、心も強くなる。
「姿」が語る人になろう。
見ただけで“あ、この人は本気だな”と伝わるように。
それが自分の価値を高めて、信用・信頼高めて。
自分を「凛々しく」「鴻鵠の志」ある人物にします。
凡事徹底
準備は怠りなくしろ。
しかし、実行に移す時が来たら、準備半ばでも行動しろ。
たぶん…。ナポレオン
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
まずは、基礎・基本を抜けもれなくやる。
凡事徹底。これは呼吸のごとくだね。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
だが、しかし、「徹底してやる」のだが、
「工夫しなきゃいけない」ときが来たら工夫していく。
いいや、その時では遅いかも。
ただの凡事をやっているが…うまくできない。
ならば、工夫する。
その凡事が何となくできたなら、すぐに次へと進む。
かまわない。すぐさま次に進もう。
「凡事」を疎かにするの?
いいえ。次に進み、また凡事に戻る。
途中からは交互にやるぐらいのつもりで。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
準備は怠りなくしろ。
しかし、実行に移す時が来たら、準備半ばでも行動しろ。
たぶんナポレオン。
凡事とは何か。
先にも書きましたが、
凡事徹底。
やり込んでいれば、ある日誰かの動きを見ていて気付くはず。
「あれ、こうすればもっと良い動きで技が活きるのでは?」
「あれ、あの動きに対して、僕はこう動けば対応できるのでは?」
ハッキリとではないけど、「ナニカ」が見えてきます。
みんな「凡事を徹底ね
保護者の方・提案です。
「褒める」より難しい?
子どもの心が本当に育つ「3つの関わり方」]
…本当かどうかは定かでない?(^^♪
親のジレンマ、よく分かります
道場での稽古を見ていて、
「もう少し真剣にやってほしいな…」
「またふざけてる…」
そう思ったことありますよね?
親として当然です。
我が子に「ちゃんとやってほしい」と思うのは、愛情がある証拠。
だけど、その“ひと言が、実は子どもの心の中では違う響き方をしていることもあります。
空手の現場で長年見てきて、僕はこう感じます。
「正しく導こう」と思うほど、親の顔が★先生。になってしまう。
けれど、子どもがいちばん求めているのは「味方」と感じます。
今日はそんな想いから、僕が保護者のみなさんに伝えたい、
3つの関わり方★をお話します。
【1】説教より、まず「聴く」
嫌われ役はボクがします。
稽古の時に「叱る」や「怒る」役は、僕がやります。
それが僕の役目かな。
親御さんにはぜひ、“聞き役”に徹してほしい。
たとえば、家で子どもにこう聞いてみるのはどう。
-
「今日、楽しかった?」
-
「難しかった?」
-
「みんなと協力できた?」
-
「痛かった?」
-
「怖かった?」
たとえ「うまくできなかった」と言っても、否定しなくていいんです。
「そうか」「疲れたね」「難しいよね。」
――それだけで十分な気がしますよ。
そこに正解は要りません。
“聞いてもらえた”という安心感が、子どもの心を整えるのでは。
そしてもし「なんで怒られたのかな?」と話し出したら、
一緒にその“理由”を探していく。
答えを急がず、子どもの世界を一緒に覗くつもりで。
解決は、子ども自身がいつか見つけますよ。
フォローが必要そうなとき、その言葉を探しましょうね。
【2】「褒める」よりも「認める」なんてどうですか。
結果より“過程”を見てあげてください
僕はよくこう言います。
「認めることって、褒めるより難しいですよ」と。
“褒める”は結果への反応。
でも“認める”は、その前の過程への理解と共感です。
試合に出た。
練習を頑張った。
泣きながらも続けている。
そういう姿そのものに
「すごいな」
「頑張ってるね」と言ってあげてください。
それは評価じゃなくて“感動”。
「すごい結果」じゃなく、「すごい過程」を見つけてあげる。
子どもは、そのまなざしで、自分の価値を学びます。
ボクが感じている試合の内容。
「凄い。」と思ったところと、「パパママ」が「凄い」
思ったところちがいますよね。
でも、ガンバッて、日々積み重ねている凄さをかんじてね。
【3】教えるより、「一緒に考える」
教育者ではなく、“伴走者”として
子どもが相談してきた時、
つい「こうしなさい」と言いたくなりますよね。
でも、僕はあえてこう提案します。
(・・・こたえおしえてしまうんですよね・・・コレが。
わからないんじゃないかと不安にさせたくはない・あと解らないのと、思われたくない。ので・・・つい。)
「一緒に考えようか」
このひと言で、立場が変わります。
上からの指導者ではなく、隣に座る伴走者になります。
「こうすればいい」と教えるより、
「どうしたらいいと思う?」と一緒に悩む。
その時間が、子どもの“考える筋肉”を育てます。
僕はいつも、「カラテのときだけでも、ぜひ試してください」と言っています。
日常全部を変える必要はありません。
でも、道場での一瞬に“伴走する親”がいると、子どもの心は確実に変わります。
子どもたちは、僕らが思うよりずっと複雑です
ゲームもしたい。遊びたい。だけど今は道場に来ている。
それって、子どもなりに★戦ってるんです。
僕ら大人だって、「今日は仕事したくないなぁ」って日ありますよね?
彼らはそれを、日々乗り越えています。
空手は、その経験の一つ。
最後に──「子どもの言葉を楽しむ」
僕が伝えたいのは、これに尽きます。
「子どもの言葉を、楽しんでください。」
評価じゃなく、感動。
「ちゃんと聞いてあげよう」じゃなく、
「聞けてうれしいな」でいい。
子どもの言葉は、成長の証です。
怒りや涙も、心が動いている証拠。
それを楽しめる親子関係が、一番強くて、一番優しい。
押忍。
これが、僕が空手を通して感じた“子どもの心を育てる3つの関わり方”です。
叱るのは僕の役目。
親御さんは、どうか一緒に感じて、一緒に笑って、一緒に悩んであげてください。
(学校の先生ってすごいな。と思うここ十数年)
✊ まとめ
1️⃣ 聴くこと中心に。
2️⃣ 結果より過程を認める。
3️⃣ 教えるより一緒に考える。
この3つ。
どれも難しいけど、どれも「愛」がなきゃできない。
だからこそ、子どもの心は育ちます。
愛だよ。愛。