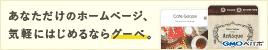ブログ
昇級おめでとう!
試合シーズン🌸
やる気の差ではありません――同じ指導なのに反応が違う理由 |パパ&ママへ。
※この記事は、道場で子どもたちと向き合う中で感じたことを、 親御さん向けに噛み砕いて書いたものです。 専門的な心理学の話ではありません。 一人の指導者・大人の視点として読んでください。
同じことを教えているのに、反応が違うのはなぜ?
道場でよくある光景です。
同じ説明をして、 同じ練習をして、 同じ声かけをしているのに――
・素直に取り組む子 ・ふざけたように見える子 ・黙り込む子 ・そっけない返事をする子
反応は、まったく違います。
これ、 「やる気の差」でも 「性格の良し悪し」でもありません。
子どもは、それぞれ“守り方”が違う
子どもはみんな、 自分なりのやり方で
心を守っています。
ある子は、 目立つことで自分を守ります。
・元気に振る舞う ・おどける ・ふざけて見せる
でも内心では、 「出来ないと思われたくない」 「恥ずかしい」
そんな気持ちを抱えていることも多い。
できないと思われたくない子もいる
一方で、
・考えてから動く ・慎重 ・失敗を嫌う
そんな子もいます。
このタイプの子は、 「分かりません」 「出来ません」
と言うこと自体が、とても苦手。
だから、 ・曖昧な返事 ・調子が悪そうな態度 ・素っ気ない反応
になってしまうこともあります。
どちらも「悪い態度」ではありません
大事なことなので、はっきり書きます。
どちらも、悪い子ではありません。
ふざけているように見える子も、 そっけない子も、
不安や緊張を 自分なりに処理しているだけ。
思春期は、さらにややこしくなる
成長すると、 「自分で決めたい」という気持ちが強くなります。
その結果、
・親の言葉に反発する ・会話が減る ・態度がきつくなる
そんなことも起きます。
これは、 親御さんの育て方が悪いわけではありません。
成長の過程で、ほぼ全員が通る道です。
親ができる一番大事なこと
親御さんにお願いしたいのは、
「比べないこと」
兄弟と比べない。 友達と比べない。 昔の自分と比べない。
その代わりに、
・昨日より少し前に出た ・前より続けられた ・逃げずに挑戦した
そんな過程を見てあげてください。
褒めるより、「認める」
「すごいね!」 「上手だね!」
もちろん悪くありません。
でも、それ以上に大事なのは、
「頑張ってたね」 「工夫してたね」 「逃げなかったね」
結果ではなく、 そこまでの道のりを 言葉にしてあげること。
指導者は、子どもを“育てる人”ではない
少し意外かもしれませんが、
指導者は、 子どもを親の代わりに育てる存在ではありません。
子どもが挑戦できる 「場」をつくる人。
親御さんと指導者で、 役割は違っていていい。
最後に
子どもは、 大人が思っている以上に、 ちゃんと見ています。
見られていることも、 信じられているかどうかも。
焦らず、 比べず、
「この子なりのペース」を 一緒に信じていきましょう。
それだけで、 子どもは少しずつ前に進みます。