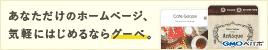試合出場への心構えと実践
試合に出たいという気持ち、とてもよく分かります。
そして、「次、みんなが出るから出たい」その気持ち。
それもよくわかります。
一歩踏み出す素晴らしいきっかけになるのもわかります。
しかし、友達が出るから出る。と、なると・・・道筋と経験の意味と結末の価値と・・
大切さが消えるではないか・・・。
試合への準備と意識
「出場するだけの練習・意識ができてない」「間に合わない」と感じているのであれば、それは正直な気持ちであり、自分と向き合えている証拠ですね。
それは大事です。
中途半半な稽古で試合に出ることは、怪我のリスクを高めるだけで。痛い経験だけで学びにはならないでしょう。
試合に出るということは、単に勝敗を決める場ではありません。
それは、これまでの稽古の成果を試し、自分の現在地を知り、そして未来の自分を創り上げるための貴重な機会です。
「どうしようかな…」「もう少しうまくなったら…」「強くなったら…」と考える気持ちも理解できます。
でもね。そんな日は残念ながらありません。
経験し、反省し、工夫し、新たに挑戦する。
その繰り返しこそが自分を成長させます。
どうしよう・・・どうしようかな・・。時が来て行動なければ・・。
時間だけが過ぎていくのはもったいないことです。
試合がもたらす成長と継続の重要性
一度でも試合に出れば、その経験は必ず次に繋がるのだろうか。
試合の間隔が空きすぎると、その経験を活かしきれないばかりか、ほぼ一からスタートとなると思ってください。緊張だけが大きくなり、そこからの再スタートになる可能性もあります。
だからこそ、あまり間を開けずに、前回の反省点、工夫点を意識して稽古し、再挑戦したほうが良いのでは。
試合での緊張は誰しもが感じるものですが、その中で自分がどうだったか、良かった点は何か、反省点や改善点は何かを具体的に見つけること。
そして、そこから次の稽古へと活かすことで、確実にレベルアップしていくでしょう。
仕事に置き換えてもこれからの人生のことを考えても。
行動して、公開とか反省とか、工夫とか、成功体験とか。なくてはならないこと。
そのままで終わらせることがどれほど良くないことか。
(はい、ボクは反省しています。(*^^*))
挑戦することの価値
「弱い」「チカラがない」と感じるでしょう。
それでいい。それがいい。
そこから対策を練り、工夫し、新たな挑戦をすることで、自身を創り上げ、表現することができます。
友達が出るから出る、ではなく「自分自身が挑戦したいから出る」という強い気持ちが大切です。
現実的に、挑戦してみたいと決断して、一人で道場に稽古に来て、練習して、試合に出て、負けたけれども、練習で得たものを試合でやってのけた子もいます。
素晴らしい間合いの取り方デシた。非力タイプですが、練習したこと自分ができること表現できてました。感激しました\(^o^)/
次の決断できるなら、間合いの取り方が抜群にうまい選手になることでしょう。
気持ちがあれば、周りも全力で応援したくなります。怖いという気持ちは、あなたも、私も、みんな同じです。だからこそ、その壁を乗り越えた時の喜びは、何倍も大きいのです。
試合感覚と緊張、そして決断
試合感覚が空いてしまうと、たしかに緊張が大きくなるのはよくあることです。これは、経験が少ない、あるいはブランクがあることによって、未知の部分が増え、不安が募るためです。
個性にも夜でしょうけど。
その緊張は決して悪いものではありません。
それは、真剣に試合に臨もうとしている証拠でもあります。
「出るか出ないかしっかり考え、決断の時が来たら、決断する」とても重要です。
- 「出る」と決める場合: 決めたら、そこからは後戻りせずに練習に集中しましょう。中途半端な気持ちではなく、「やるぞ!」という強い意志を持って臨むことが、良い結果に繋がり、そして何より自分自身の成長になります。怪我のリスクを避けるためにも、体調管理や十分な準備が不可欠です。本当に出る出ないは横においておきましょう。
- まず、目標・目的に向かいましょう。
- 「出ない」と決める場合: それもまた一つの決断です。無理に出場して心身に負担をかけるよりも、出ない。応援に回る。何なら観察してコーチとして挑戦する。
- 厚かましいと思わず観察して助言してみましょう。才能あるかもよ。ヤツテミヨウ。
どんな決断をするにしても、大切なのは自分自身と向き合い、納得して決めることです。そして、一度決めたら、その決断を信じて前向きに進んでいくことが、あなたの成長に繋がります。
もちろん「いや、やらないと決断したら、やりたくて仕方がない。」
それは君の魂の部分の本音かも。
再度、親とか友達とか相談して自分で行動起こしてみよう。
大切なこと
しっかりと考え、計画を立てる。
しかし、時が来たら迷わず行動する。
- ウジウジ考えず、どんどん挑戦する。
- 「出るなら出る」と決断する。
- 中途半端な稽古で出ない。怪我のリスクを避けるためにも、準備をしっかりする。
- 経験を通じて反省し、工夫し、次に繋げる。
緊張の先にこそ、大きな達成感や学びがあることを忘れないでください。悩むのではなく、考え決断。時が来たら挑戦することを選び、そのための準備に全力を尽くす。このサイクルを回すことで、きっとあなたは成長し、さらに強くなれるはずです。
僕達は君の挑戦を心から応援します。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48f8130e.b2ed0020.48f8130f.999ef9ba/?me_id=1255411&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fauc-garlic%2Fcabinet%2Fkuensan%2Fimgrc0105205640.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)