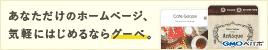ブログ
質問する技術④。知識をひけらかすのではなく、相手の成長のためにどう「渡す」か
「質問が出ない」そのとき——これでいいのだろうか?
知識をひけらかすのではなく、相手の成長のためにどう「渡す」か。
これは、僕が今もずっと試行錯誤している部分です。
指導していて、ふと立ち止まる瞬間があります。
「質問が出てこない」のです。
ここまで読んでくださった方の中には、
「小嶋先生の指導なら、みんな納得してて質問なんて出ないんじゃないですか?」
モット褒めてもいいよ。
そんなふうに言ってくださる方もいるかもしれません。
実際にやってみて、体で実感してもらう稽古を大切にしています。
そこには、理論や理屈もありますし、経験からくる現実も深く込められている自負もあります。
生徒たちが「先生の言う通りにすれば間違いない」と信頼してくれていることも感じています。
それは、指導者として本当に光栄なことです。
でも、それでも僕の心の中にはいつも、
「コレで・・いいのかなぁ~?」という問いが横たわっているんです。
★なぜ、質問が出ないのか?
僕は基本的に、高校生以上には「一つ教えたら、黙って見ている」スタイルでいます。
質問が出てきたら、その先を教えよう。そう思っているのですが……。
我慢できずにくちだしするけどね。
サンドバッグを打つ手は止まらない。
それぞれ真剣に稽古に向かっている。
それはとても誇りに思えます。
でも、質問がない。
不思議でならないんです。
僕はいつも稽古中に、疑問が次々に浮かんできた人間でした。
彼らは——
-
僕に聞いても仕方ないと思っているのか?
-
実はしっかり理解して、黙って吸収しているのか?
-
僕の指導が「説明の理解が、しにくい」から、逆に言葉にできないのか?
たまに、万人受けする言い方をすべきか……と考えることもあります。
それっぽく、素晴らしい系の言葉並べたくる。がいいのかな。
でも、世間で「もっともらしく」語られていることが、
すべての人にとって本当に役に立つかというと、そうでもない。
すごい人の話が、普通の人に役立つとは限らない。
でも、有名な選手等が言うと鵜呑みにしている子もいる。
「きみはタイプ違うと思うが・・・。」
有名選手は、さすがトップなだけ有る。才能があるのです。
きみは普通。
きみに向いているスタイルから作り込んで、トップに喰らいつこうよ。
それともボクがきみの才能に追いついていないのか・・・、。
質問が出ない理由——僕が考える3つのパターン
-
完全に理解し、納得している。
これは、理想的な状態です。 -
理解しているけれど、「問いを立てる力」がまだ育っていない。
もっと深掘りできる問いに、気づけていないだけかもしれない。 -
実は理解しきれていない。でも、「こんなこと聞いていいのかな」と遠慮している。
理解できない自分を、どこかで「申し訳ない」と感じているのかもしれない。
2番目と3番目の可能性を考えると、
僕の中でまた、「これで本当にいいのだろうか?」という問いが頭をもたげてくるんです。
質問されて、すぐに言葉に出来ないけれど、頭の中のイメージは出来てます。言葉として表現するのが難しいのです。そして今、やって見せることが出来ない現実があります。
許してくれ。
★僕が目指している指導
僕は、ただ技を教えたいわけではありません。
生徒たちが、自分で課題を見つけ、自分で答えを探し、自分で成長していけるようになってほしい。
だからこそ、僕の指導は「答えを教える場」であると同時に、
「問いを見つける手助けをする場」でなければならないと思っています。
【難しいですね。】
生徒が「これだ!」と納得できるほど、質の高い指導を追い求めながら、
同時に彼らが「なぜ?」「もし○○だったら?」と自ら問いを立てるような場もつくっていきたい。
「質問が出ない」ことに満足せず、
その奥にある可能性を、僕はもっと引き出したいんです。
★僕には先生がいませんでした
かっこつけて言うなら、**「我以外、皆我師」**です。
僕が格闘技を始めたころ、練習する場所も、人も、圧倒的に少なかった。
キックボクシングのジムなんて、今のようにありませんでした。
聞きたいことは山ほどあるのに、聞く相手がいない。
練習相手もいない。
たまに弟がミットを持ってくれるだけ。
だから僕は、ひたすら「試す」しかなかった。
考えて、仮説を立てて、試合の3分で確かめる。
あーでもない、こーでもない。
無駄が多すぎるかもしれない。
でも、やってみないとわからない。
そんな試行錯誤の連続でした。
誰かに聞きたくても、
ようやく聞けたときには、相手の答えがマチマチ。
時には、偉そうで上から目線で返されてしまったこともあります。
聞きたいのは、そんなことではない・・・。
……いや、僕が素直じゃなかっただけかもしれません(笑)。
★今、僕がやるべきこと
だからこそ今、僕が目指すのは、
「答えを与える」よりも、「問いを引き出す」指導。
質問が出ないときこそ、自分の指導を振り返る。
生徒が“自分から聞きたくなる”空気を、もっと意図的につくる。
それが、僕がこれからも挑み続けるテーマです。
ヤル、マカシとけ。
今日の練習で、誰かがぽつりと質問してくれるかもしれない。
その一言が、全体の成長につながるかもしれない。
その種をまくのが、僕の仕事。
問いの芽を育てる場所をつくるのが、指導者だと思っています。
と、思っていますが。
むずかしい・・・。
質問まつより、ドンドン、指導したほうが早い・・・。
これがイケないのか。
まつのも技術が必要ですね。